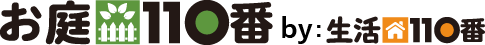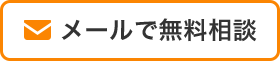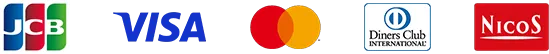「庭にシンボルツリーになる落葉樹を植えたい」と思っても、種類が多くて迷ってしまうのではないでしょうか。
落葉樹は葉や花、実などさまざまなものを楽しめます。
シンボルツリーを選ぶうえで大切なことは、何を楽しみたいのか明確にしておくことです。
シンボルツリーにおすすめの樹木を4ジャンルにわけてご紹介します。それぞれの特徴を知ってお気に入りの落葉樹を見つけましょう。
- 落葉樹と常緑樹の違い
- 葉・花・実に特徴のある落葉樹の種類
- シンボルツリーの選び方
目次
落葉樹のシンボルツリーの特徴
落葉樹とは、春には葉が茂り冬になると葉が枯れて落ちる樹木です。
落葉樹は秋から少しずつ休眠期に入り、成長を止めたり緩やかにしたりするため、蓄えた栄養を逃がさないように、水分の逃げ道となる葉を落とします。
種類によっては葉の色が変わったり美しい花が咲いたりするものもあり、季節によって見た目の雰囲気が変わるため、庭の象徴となるシンボルツリーにもおすすめです。
季節の移ろいを感じたい方は、ご紹介する落葉樹からお気に入りの樹木を探してみましょう。
なお、基本的に葉が落ちる季節が決まっているため、こまめな掃除は不要ですが、大量の落ち葉を一度に掃除する必要があります。
常緑樹とは何が違う?
季節によって見た目にわかりやすい変化を見せる落葉樹に対して、常緑樹はいつでも緑の葉を茂らせています。
冬でも寒々しい印象にならず、明るい庭造りが可能です。
夏の暑さにも冬の寒さにも強い種類が多く、葉の密度が高い種類を選べば目隠しの効果も高まるため、家の敷地と外の境界線にするのもいいかもしれません。
落葉樹のように大量の葉が一気に落ちることはありませんが、寿命を迎えた葉は散ります。
大がかりな掃除の必要はありませんが、こまめに落ち葉を処理する必要はあるので覚えておきましょう。
個性的な葉が楽しめるおすすめ落葉樹4選
落葉樹といっても、樹木の種類によって魅力的な部分はさまざまです。
まずは個性的な形や色の葉を楽しめるカツラ、コナラ、イチョウ、ヤマモミジの4種類をご紹介します。
カツラ
カツラは、丸みのあるハート形の葉が特徴的です。
日本に自生している種類で、かつ自然に樹形が整うため、初心者でも育てやすいといわれています。
公園や並木道、神社などあらゆる場所に植えられており、天然記念物に指定されているものも多いです。

| 樹高 | 大きいものは30メートル以上になる |
| 葉の特徴 | 花が終わってから萌黄色の葉がつき、成長すると鮮やかな緑、落葉期には黄色へと変化 |
| 花の特徴 | 4~5月にイソギンチャクのような形の赤い花が咲く |
| 実の特徴 | 10~11月に細長い実をつける |
| 育てやすい環境 | 湿り気のある土壌で日当たりのいい場所 |
| 剪定 | 落葉期に混みあった部分だけ剪定する |
| お手入れのポイント | 大木になることを考慮して広いスペースを確保しておく |
| 幹の雰囲気 | 茶色と灰色の中間のような色で、経年により縦に割れ目ができる |
落葉時期の葉から香りがするのですが、「醤油せんべいのよう」「焼き菓子みたい」「キャラメルに似ている」など人によって感じ方に違いがあります。
そのため、自分で育てたカツラの香りを楽しむのもおすすめです。
コナラ
コナラは、戦前燃料用の木材としてよく使われていた樹木で、山や公園に植えられていることが多いです。
葉の形はノコギリの刃のようになっていて、若葉から落葉期の葉までの色味や質感の変化を楽しめます。

| 樹高 | 基本的には15~20メートルで、大きいものは30メートルほど |
| 葉の特徴 | 若葉は産毛に覆われて白っぽく、成長すると深い緑に変化し、徐々に紅葉して落葉期には茶色くなって葉を落とす |
| 花の特徴 | 4~5月に小さな黄色の花が垂れ下がるように咲く |
| 実の特徴 | 楕円形のどんぐりがなる |
| 育てやすい環境 | 年間通して日当たりのいい場所 |
| 剪定 | 落葉期から開花時期の前までに剪定して風通しをよくする |
| お手入れのポイント | できる限り長く日が当たる場所に植える |
| 幹の雰囲気 | 灰色っぽい色をしていて、不規則に縦方向の裂け目がある |
まんべんなく紅葉したコナラの木は美しいですが、カツラ同様大木になる可能性があるため、気に入った場合は広めのスペースを確保しておきましょう。
また、どんぐりは動物たちのエサになることもあるため、野鳥などの姿を見ることができるかもしれません。
イチョウ
扇のような形の葉が特徴的なイチョウは、街路樹として植えられていることも多く、比較的なじみ深い樹木です。
秋に色付く様子が代表的な姿ですが、他の特徴や魅力も見ていきましょう。

| 樹高 | 20~30メートル |
| 葉の特徴 | 開花とともに緑の葉が出てきて、10月頃から黄色に色付き、多くの葉は明るい黄色を保ったまま落ちる |
| 花の特徴 | 4月頃に黄色と茶色の間のような色の花が咲く |
| 実の特徴 | 花後に銀杏の実がなり、葉が色付くよりも先に熟して落ちる |
| 育てやすい環境 | 暑さ・寒さ・乾燥に強く、基本的に日当たりがよければ問題なし |
| 剪定 | 落葉期に風通しを悪くする枝と樹形を崩す枝を切る |
| お手入れのポイント | 大木にしたくない場合は剪定で大きさを調整する |
| 幹の雰囲気 | 灰色がかった茶色で、縦に浅く割れ目ができる |
葉が色付く10月~12月が観賞に最適な時期です。
あわせて、銀杏の実の好きな方は秋の味覚も楽しむことができます。
ただし、大量の銀杏の実が落ちたときのニオイが嫌な方は、実のつかない株を植えましょう。
ヤマモミジ
ヤマモミジは7~9つにわかれた葉の形が特徴的な樹木です。
庭木だけでなく盆栽でも人気があります。
日の当たり方によって紅葉の時期に葉が何色に染まるかが変わる点も楽しみのひとつです。

| 樹高 | 基本的には5~10メートルで、大きいものは15メートル |
| 葉の特徴 | 5月頃に鮮やかな緑の葉が開き始め、10~11月に赤く色付き、11月下旬には落葉する |
| 花の特徴 | 5~6月に小さな紅色の花が咲く |
| 実の特徴 | 子孫を残すための小さな豆に羽が生えたような実がつく |
| 育てやすい環境 | 湿度を保つ土のある日当たりのいい場所 |
| 剪定 | 11月下旬の落葉が始まる頃に不要な枝や葉、芽を減らす |
| お手入れのポイント | 美しい紅葉のためには寒暖差のある場所での栽培が必要 |
| 幹の雰囲気 | 灰褐色でなめらかだが、経年とともに縦に割れ目ができる |
モミジは赤く色付くのが有名ですが、日当たりによってオレンジや黄色に染まる葉もあるため、1本の木で色のコントラストを楽しむことができます。
年月とともに質感が大きく変わる幹にも注目です。
葉と花のバランスが美しい落葉樹4選
葉だけや花だけがメインではなく、葉と花のバランスを楽しむ落葉樹もあります。
アオダモ、エゴノキ、スモークツリーの3種類です。
花の色味や大きさが目立つものもありますが、葉の緑とのコントラストにも注目してみてください。
アオダモ
アオダモは、生長がゆっくりで大きくなり過ぎないよう管理しやすい初心者にもおすすめの樹木。
枝の先端に咲く白っぽい花と葉のバランスが魅力的です。

| 樹高 | 基本的には5~10メートルで、大きいものは15メートルほど |
| 葉の特徴 | 縦長で明るい緑色 |
| 花の特徴 | 4~5月に白やアイボリーの細長い花が密集して咲く |
| 実の特徴 | 花後にしおれた葉のような実がつく |
| 育てやすい環境 | 朝は日が当たり夕方日陰になるような西日の当たらない場所 |
| 剪定 | 12~2月に根元から伸びる枝や風通しを悪くする枝を切る |
| お手入れのポイント | 木が小さいうちは病害虫に注意が必要 |
| 幹の雰囲気 | 薄い灰色のような色で、ところどころ白っぽい部分がある |
アオダモの花は基本的に白っぽい色をしていますが、ものによって真っ白に近いものやアイボリーっぽいものなどさまざまです。
また、明るい色味の幹も他とは違う魅力があります。
エゴノキ
果実をかじったとき感じるエグ味に由来してエゴノキという名前がつけられましたが、開花時は鐘が連なるような見た目が美しく、英国でスノーベルと名付けられています。

| 樹高 | 7~8メートルが一般的で、大きいものは10メートル以上 |
| 葉の特徴 | 卵型の葉が枝に沿って左右交互に生えている |
| 花の特徴 | 5~6月に枝から垂れ下がるようにして地面を向いて花が咲く |
| 実の特徴 | 花後にくすんだ白っぽい色の実が垂れ下がってつく |
| 育てやすい環境 | 日当たりがよく強い西日を避けられる場所 |
| 剪定 | 12~3月に日が当たりにくい枝や伸びすぎた枝を切る |
| お手入れのポイント | 強めの選定は樹形を乱すことになるため要注意 |
| 幹の雰囲気 | 青みがかった茶色で縦に細かいシワが入る |
新緑の季節から葉や実を落とす休眠期まで、季節ごとに違った楽しみがある樹木です。
また、代表的なのは白い花ですが、ピンクの花を咲かせる種類もあります。
スモークツリー
スモークツリーは、花が咲いたあとのふわふわした花穂が特徴的な樹木です。
暑さにも寒さにも強いため、基本的には日本全国あらゆる場所で育てられます。

| 樹高 | 3~4メートル |
| 葉の特徴 | 緑色の品種と赤紫色の品種がある |
| 花の特徴 | 5~6月に小さな花が咲き、6~9月に綿菓子のような花穂になる |
| 実の特徴 | 焼いたそら豆のような実が花穂の先端につく |
| 育てやすい環境 | 水はけのいい土壌で、日当たりがよく強風の当たらない場所 |
| 剪定 | 12~2月に内側に向かって伸びる枝や伸びすぎた枝を切る |
| お手入れのポイント | 根が横に広がるため、周りのスペースをあけておく |
| 幹の雰囲気 | やや灰色がかった茶色でウロコのようなひび割れができる |
スモークツリーの花穂は、写真にあるように複数の種類があります。
葉の色も品種によって異なるため、庭の雰囲気に合わせて色味を考えるのも楽しいのではないでしょうか。
鮮やかな花を楽しむ人気の落葉樹3選
花は開花時期が決まっているため、長期間観賞できません。
しかし、花を見て特定の季節の訪れを感じるなどの楽しみ方はできます。
花の色も形もまったく異なるサクラ、ライラック、モクレン、ハナミズキ4種類の魅力をご覧ください。
サクラ
サクラは日本で古くから愛される国花で、世界でも日本をイメージする樹木として有名です。
ソメイヨシノのように5枚の花弁を開くものから、花弁の多い八重桜や簾のように花をつけるしだれ桜などさまざまな種類があり、それぞれ開花時期が異なります。

| 樹高 | 3~20メートル |
| 葉の特徴 | 花が散りだしてから若葉が芽吹き、秋に紅葉して徐々に散る |
| 花の特徴 | 2~4月に開花するものが一般的で、花弁の数や咲き方だけでなく花の色味も白に近いものから濃いピンク色まで多種多様 |
| 実の特徴 | 緑の葉の隙間に赤と黒の実がつく |
| 育てやすい環境 | 日当たりがよく強い西日の当たりにくい場所 |
| 剪定 | 12~3月に混み合った枝を切る |
| お手入れのポイント | 樹形が乱れやすいため、丁寧な剪定が必要だが、強く剪定しすぎると数年間花が咲かなくなるおそれがある |
| 幹の雰囲気 | 横向きの裂け目のような模様があり、色は品種によって異なる |
大きく育つ品種は広く根を張るため、広めのスペースが必要です。
また、日当たりの悪い場所に植えてしまうと、日に当たらない部分が枯れるおそれがあるため、栽培環境には細心の注意を払いましょう。
サクラは春に咲く花が特に魅力的ですが、庭に植えれば季節によって色を変える葉や葉に隠れるようにつく実もよく見えます。
細部に注目すれば新たな魅力に気付けるかもしれません。
ライラック
ライラックは寒さに耐性のある樹木で、寒冷地の街路樹などになっています。
たくさんの花が房状に密集して咲き誇り、花の色は白やピンク、薄い紫や青みをおびた色などさまざまです。

| 樹高 | 1~6メートル |
| 葉の特徴 | 4~12センチメートルにもなる大きな葉がつく |
| 花の特徴 | 4~6月に小ぶりな花が房状に集まって咲いたものがいくつもの枝先につき、いい香りがするといわれている |
| 実の特徴 | 花後に小さくて細長い黄緑色の実がつく |
| 育てやすい環境 | 涼しくて日当たりがよく水はけのいい土がある場所 |
| 剪定 | 12~2月に枯れた枝や樹形を乱す枝を切る |
| お手入れのポイント | 暑さに弱く、萌芽力も弱いため、栽培環境と剪定方法に注意 |
| 幹の雰囲気 | やや明るい茶色をしていて、経年により縦にいくつもの割れ目ができる |
ご紹介した他の樹木と比べて樹高が低めで、お手入れはしやすいかもしれません。
また、開花時期が比較的長いため、鮮やかな花を長く楽しみたい方にはおすすめです。
モクレン
モクレンは花弁の色が特徴的な樹木です。
よく似たハクモクレンも同じモクレン科の樹木ですが、花弁の色や樹高、枝の広がり方などがまったく異なります。

| 樹高 | 3~5メートル |
| 葉の特徴 | 葉の縁が波打つような形をしている |
| 花の特徴 | 3~4月に開花する花の色は、内側が白く外側が濃いピンク色をしている |
| 実の特徴 | 花の外側と似たような色の凸凹な実がつく |
| 育てやすい環境 | 枝が横に伸びるため、横幅を広くとれる日当たりのいい場所 |
| 剪定 | 花後か12~2月に伸びすぎた枝や絡んでいる枝などを切る |
| お手入れのポイント | 自然に樹形が整うため、不要な枝を切るだけでいい |
| 幹の雰囲気 | 白っぽい灰色をしていて、比較的なめらかな質感 |
独特な色の花は庭を鮮やかに彩りますが、開花期間が3~4日ととても短いです。
わずかな期間でもグラデーションカラーのような美しい花を楽しみたい方におすすめします。
ハナミズキ
ハナミズキは、公園などに植えられていることも多い樹木です。
比較的生長がゆっくりで自然に樹形が整うため、メンテナンスしやすく人気があります。
ハナミズキの花弁に見える部分は、苞(ほう)と呼ばれる葉の一種で、本来の花は苞の中心に小さく集まっている部分です。
しかし、今回は見た目の印象を優先して苞の部分も含めたものを花として紹介します。

| 樹高 | 4~10メートル |
| 葉の特徴 | 白い品種は緑一色の葉、ピンク系の品種は一部が赤い葉が芽吹く |
| 花の特徴 | 開花時期は4~5月で、色は白いものとピンク系統のものがあり、苞の先が波打つことで花弁がハート形に見える |
| 実の特徴 | 秋になると赤くてつやのある小さな実がつく |
| 育てやすい環境 | 乾燥しにくい土壌で日当たりのいい場所 |
| 剪定 | 12~2月に樹形を乱す枝を切り、5月に混み合った枝を切る |
| お手入れのポイント | 乾燥を嫌うため、株元に強い日差しが当たらないようにする |
| 幹の雰囲気 | 灰色と茶色と緑色が混ざったような色味で、ウロコをまとったような細かいひび割れが特徴的 |
暑さにも寒さにも強くはありませんが、栽培環境がよければ鮮やかな赤い実がたくさんついたり葉が色濃く紅葉したりする場合もあり、魅力の多い樹木です。
花と実で季節の変化を楽しむ落葉樹2選
落葉樹は美しい花と特徴的な実の観賞を楽しむのもおすすめです。
花を楽しむ品種と実を楽しむ品種の異なるウメと、独特の実をつけるヤマボウシの2種類をご紹介します。
ウメ
ウメには花を観賞するための花ウメと食用の実を育てることが目的の実ウメが存在しますが、今回は花と実の両方を観賞して楽しむことができる花ウメをご紹介します。

| 樹高 | 5~10メートル |
| 葉の特徴 | 丸みのある葉をつけるが、先端は尖っている |
| 花の特徴 | 白い花を白梅、赤に近いものやピンクの花を紅梅と呼び、2~3月になると細い枝に小ぶりな花がたくさん咲く |
| 実の特徴 | 食用のウメと見た目の違いはほとんどなく、味に渋みがあるなどの理由で食用に不向き |
| 育てやすい環境 | 株が蒸れないよう日当たりと風通しのいい場所 |
| 剪定 | 6~7月に伸びすぎた枝や混み合った枝を切る |
| お手入れのポイント | 剪定を怠ると花付きが悪くなったり枯れたりするおそれがある |
| 幹の雰囲気 | 黒っぽいこげ茶色でくねくねしている |
ウメは花弁の少ない品種からボリュームのある花が咲く品種までさまざまな種類があります。
枝が簾のように地面に向かって垂れているしだれ梅も魅力的です。
また、食用には不向きですが、ウメの実が徐々に熟していく様子も季節の移ろいを感じる楽しみのひとつになります。
ヤマボウシ
ヤマボウシは、開花時の姿がハナミズキによく似ていて、葉の一部である苞が花弁に見える点も同じです。
観賞用に品種改良され、花の色や葉の柄などが異なるさまざまな種類があります。
独特な見た目の実をつける点も魅力的です。

| 樹高 | 10~15メートル |
| 葉の特徴 | 開花時の葉は色濃い鮮やかな緑色をしている |
| 花の特徴 | 6~7月に花弁のような苞が開花する |
| 実の特徴 | 小さなとげがついているような表面をした赤い実がつき、食用にもなるが好んで食べる人は少ない |
| 育てやすい環境 | 水が浸透しやすい土壌で、日当たりのいい場所 |
| 剪定 | ほとんど必要ないが、気になる場合は12~3月に枝を間引く |
| お手入れのポイント | 風通しが悪いと病害虫被害にあいやすい |
| 幹の雰囲気 | 赤みのある茶色で、経年とともにウロコがはがれるように皮がはがれる |
ヤマボウシは初夏から秋にかけての変化が特に注目です。
かわいらしい花や実を観賞して楽しみましょう。
また、ウロコのように樹皮がはがれる様子も魅力のひとつです。
視覚でも味覚でも楽しめる落葉樹2選
最後にご紹介するのは、花や葉を観賞するだけでなく食用の実を楽しむことができる落葉樹です。
おすすめするジューンベリーとアンズの2種類は、実の楽しみ方も詳しく解説します。
ジューンベリー
ジューンベリーは小さな赤い実をつける樹木です。
6月に実をつけるため、ジューンベリーと名付けられました。
暑さにも寒さにも耐性があり、初心者でも育てやすい果樹です。

| 樹高 | 3~10メートル |
| 葉の特徴 | 丸みがあって葉脈がはっきりと見えるのが特徴的 |
| 花の特徴 | 3~4月に真っ白な花が枝先に集まって咲く |
| 実の特徴 | 花が散る頃から徐々に実が膨らみ始め、6月に食べ頃になる 実の色は緑から赤、そして暗い紫へと変化する |
| 育てやすい環境 | 日当たりがよく湿り気のある場所 |
| 剪定 | 刈り込む剪定はせず、12~3月に混み合った枝を切る |
| お手入れのポイント | 収穫が遅れると鳥に食べらてしまうおそれがあるため注意 |
| 幹の雰囲気 | ベースカラーは灰色で、黄緑色の迷彩柄のような模様ができる |
ジューンベリーは紫になって熟した実が食べ頃です。
そのまま食べてもおいしいため、食後のデザートやケーキのトッピングに使えます。
たくさん収穫できたときは、水や砂糖、レモンなどと一緒に煮詰めてジャムを作るのもおすすめです。
アンズ
アンズはアプリコットとも呼ばれていて、さまざまな国で栽培されている樹木です。
生で食べるには酸味が強いため、多くのアンズは加工品として使われています。

| 樹高 | 3~10メートル |
| 葉の特徴 | 茎の部分が赤く、縁が波打っている |
| 花の特徴 | 3~4月にウメによく似た薄いピンク色の花が咲く |
| 実の特徴 | 実もウメに似ており、緑の実がついて、熟すと黄色やオレンジ色になる |
| 育てやすい環境 | 粘土質で水はけのいい土壌で日当たりのいい場所 |
| 剪定 | 12~2月に伸びすぎた枝を切り、樹高を高くしたくない場合は8月頃にも勢いのある枝を切る |
| お手入れのポイント | 未熟な果実が多い場合は、開花時期に特に未熟な実を取る |
| 幹の雰囲気 | 色は茶色で、縦にいくつも割れ目のような模様が入っている |
地球温暖化によって無農薬の栽培は難しくなっていますが、アンズはさまざまなものに加工して使えるため、家庭で育てて楽しむのに向いています。
煮詰めてジャムにしたり、シロップで漬け込んだり、干してドライフルーツにしたりして楽しみましょう。
シンボルツリーを選ぶ3つのポイント
シンボルツリーにおすすめの落葉樹は、ご紹介しただけでも15種類あります。
それぞれ異なる魅力があるため、ただ写真や情報を眺めて決めるのは難しいですよね。
シンボルツリーを決める際に注目していただきたいのは3点です。
樹高や葉、花、実の色、樹皮の色と質感が庭造りの際に与える影響を解説します。
樹高
樹高は、低木・中木・高木の大きく3つに分類されます。
一般的な分類方法とそれぞれのメリットをチェックしましょう。
低木:樹高3メートル未満
脚立などを使えば、身長が低い方でも隅々までお手入れできる場合が多いため、お手入れしやすい
中木:樹高3~5メートル
ある程度高さがあるため、外部から家の中が見えにくくなるよう目隠しとして活用できる
高木:樹高5メートル以上
強い日差しを防いだり、家の目印になったりする
剪定次第である程度樹高のコントロールはできますが、生長の限界は植物によって異なります。
庭のシンボルとして大きさを重視する場合は樹高が高くなる木を選び、自分でお手入れできるようにしたい場合はあまり大きくならない木を選びましょう。
葉・花・実の色
庭づくりは建物の色味や他の植物とのバランスも重要です。
シンボルツリーの葉や花、実の色だけを奇抜なものにしてしまうと、庭の雰囲気を壊すおそれがあります。
全体のバランスを見て、色味や雰囲気に統一感が出るような木を選びましょう。
樹皮の色や質感
色が異なるのは葉や花、実だけではありません。
多くは茶色や灰色がかった色をしていますが、樹皮にも違いがあります。
また、樹皮は色だけでなく質感もさまざまです。
なめらかな質感のものから大きな割れ目ができるもの、まだらに模様が出る木もあります。
シンボルツリーは庭の象徴になる木です。
樹皮の細かい色や質感まで注目して選択してください。
大きな庭木のお手入れはお庭110番におまかせ
水や肥料を与える作業や、実の収穫などは個人でもできます。
しかし、低木以外の大きな木は簡単に剪定できません。
剪定は樹形だけでなく、樹木の生長具合や健康を左右する重要なお手入れのひとつです。
お庭110番ではシンボルツリーの植栽だけでなく、高木の剪定もできる業者をご紹介します。
お気軽にご利用ください。