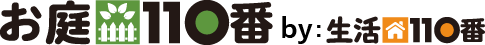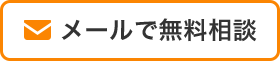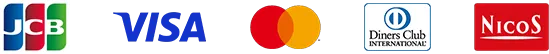庭木や植木の剪定の種類は、簡単に済むものから大掛かりなものまで数多く存在しています。樹木の種類によって適している樹形や環境が異なるからです。より美しく元気よく育てていくためには、樹木の種類ごとに剪定の種類や時期を変える必要があるのです。
このコラムでは剪定初心者の方に向け、剪定について目的からわかりやすくご紹介しています。剪定の種類やお手入れの基本を知って、育成中の庭木や植木が喜ぶ環境を整えてあげましょう。
目次
剪定の基本から学ぼう
剪定とは、植物の伸びてきた枝葉を切って形を整えるお手入れのことをいいます。庭木や植木の見た目をよくするために剪定がおこなわれますが、剪定には植物にとって以下のような大切な目的もあるのです。
【剪定の目的】
- 風通しをよくするため
- 病害虫の予防のため
- 栄養を行きわたらせるため
- 花つきをよくするため
- 大きさを整えるため
このように、剪定は植物を健康的に育てるために必要不可欠な作業です。剪定をおこなう時期は植物の種類によって異なるため、次は剪定の時期についてご紹介していきましょう。
剪定の時期は「夏」と「冬」

剪定には大きく分けて、『夏剪定』と『冬剪定』があります。
・夏剪定
その名のとおり、夏におこなう剪定のことです。夏は枝葉がぐんぐん伸びる季節であるため、伸びすぎた枝葉を切り落とすことで風通しをよくすることができます。風通しがよくなるだけでなく、日当たりもよくなるため、植物が光合成しやすい環境を整えることができるのです。また、病害虫予防や、台風で枝が折れることを防ぐ効果もあります。
・冬剪定
その名のとおり、冬におこなう剪定のことです。冬に休眠時期に入る植物なら、夏よりも大掛かりな剪定をおこなってもかまいません。休眠時期は、枝葉をたくさん切り落としても樹木に与えるダメージを最小限におさえられるため、植物に負担がかかりにくいとされているからです。
冬の時期に植物の育成にとって邪魔な枝葉は大幅に減らしておくことによって、活動を再開し始める春への準備をするという目的があります。
ただし、樹木の種類によっては適切な剪定時期が異なるため、注意が必要です。季節の花があるように、樹木もサクラやモミジなどの種類によって最盛期を迎える時期はさまざまなため、剪定時期が異なります。そこで『常緑樹』『針葉樹』『落葉樹』といった種類と適切な剪定時期についてもご紹介しておきましょう。
・常緑広葉樹
常緑樹とは、1年中葉がついている種類の樹木です。そのなかでも葉が広くて平らな形状をしているものは常緑広葉樹といいます。代表的なものに、クスノキやツバキなどがあります。剪定は、3~4月の新芽の育つ前か5月下旬~6月の新葉が落ち着いた時期が最適です。
・常緑針葉樹
常緑広葉樹と同じく、1年中葉がつく種類の樹木ですが、葉の形が針のようにとがっているのが特徴です。代表的なものに、マツやスギなどがあります。剪定は、3~4月の新芽の育つ前が最適です。
・落葉樹
落葉樹とは、気温が下がると葉が落ちる種類の樹木です。代表的なものに、サクラやハナミズキなどがあります。剪定は、12~2月の休眠時期におこなうのが一般的です。4~5月、7~8月の時期は、樹液が流れ出るなど樹木に与える負担が大きいため、ほとんど剪定はおこなわれません。
剪定の種類はたくさん!切るべき枝や剪定道具についても解説
先述のとおり、庭木によって適している剪定の種類は異なります。なにも知らずにただ枝葉を切り落とすだけでは、植物の生育環境を整えるどころか、かえって悪くしてしまうこともあるかもしれません。
また、植物ごとの剪定方法を調べるなかで「〇〇剪定がおすすめ!」など毎度といってよいほど出てくる剪定方法もあります。そのため、剪定の種類についてあらかじめ知っておくと、いざ剪定をするときも理解しやすくなるでしょう。
ここでは、剪定の種類とその方法について解説していきます。また、庭木にとって不要な枝や剪定に必要な道具についてもご紹介しています。
剪定の種類

剪定の種類には以下のようなものがあります。
- 枝透かし剪定:枝や葉の量を適度に減らして透かしていく剪定
- 切り戻し:枝を半分から3分の1ほどのところで切り、ひとまわり小さくする剪定
- 刈り込み:生垣などのように全体を均一に刈り込んで整える剪定
- 芽摘み:不要な芽を摘み取る剪定
- 花柄摘み:咲き終わった花を摘み取る剪定
- 整姿剪定:不ぞろいな枝を切って形を整える剪定
- 整枝剪定:よい枝ぶりにするために樹木の骨格を作る剪定
- 切り詰め剪定:花つきをよくするために育ち過ぎた樹形を縮める剪定
- 吊るし切り剪定:大木の枝を切るためにロープを使用して枝をおろす剪定
- 伐採剪定:根株だけを残しほかはすべて切り取る剪定
- 野透かし剪定:樹形を整えるためノコギリを使って枝を切る剪定
不要枝の種類
不要枝とは樹形を崩したり、風通しを悪くしてしまったりする樹木の生長にとって邪魔となる枝のことをいいます。不要枝には以下のような種類があります。
- 徒長枝:幹や主枝から勢いよく真っすぐ伸びて樹形を崩している枝
- 平行枝:主枝より後に平行に伸び出して日当たりを悪くしている枝
- ふところ枝:樹木の内側に出てきて枝葉が混み合う原因となる枝
- 交差枝:必要な枝に交差して伸び、樹皮を傷つけてしまうおそれがある枝
- 逆さ枝:幹の方向に逆さに生え、樹形を乱している枝
- 下がり枝:下向きに生え、樹形を乱している枝
- ひこばえ:木の根元から立ち上がる枝
- 車枝:1カ所から複数生えて、樹形や日当たりを悪くしてしまっている枝
- 胴吹き枝:幹の途中から生えて、養分を奪い取ってしまっている枝
これらの枝は、樹木にとって成長の邪魔となる枝のため、見つけたら枝の付け根から切り落としてしまいましょう。枝分かれをしている場合は、枝分かれのすぐ上の部分で切ると自然な樹形となります。
剪定に必要な道具
続いて、剪定に必要な道具についてもご紹介します。すべてそろえるのが面倒な場合は、まずは剪定バサミを用意しておくと、幅広い種類の植物の剪定で使えるためおすすめです。
- 剪定バサミ:細い枝から太い枝まで切ることができるハサミ
- 植木バサミ:細かい枝を切ることを得意とするハサミ
- 刈り込みバサミ:生垣などを作る際に使用する刃が長めになっているハサミ
- 剪定ノコギリ:ハサミでは切り落とせない太い枝を切るノコギリ
そのほか、手袋や脚立、掃除道具があれば、作業中のけが防止や作業の効率化につながるため、事前に用意しておくとよいでしょう。
業者に依頼すべき剪定
ここまで、いくつかの剪定の種類をご紹介してきましたが、そのなかには業者に依頼したほうがよいものもあります。たとえば、以下のような剪定があてはまります。
- 高木の剪定
- 真夏や真冬の剪定
- スキルが必要な剪定
高木の剪定は、長時間脚立に登りながらの作業となります。慣れていないとバランスを崩し落下して大けがをしてしまうおそれがあるため危険です。また、真夏や真冬の外での作業は体調を崩す原因となってしまうかもしれません。
先述した吊るし切り剪定や特殊な樹形の庭木なども、業者に依頼したほうがよいでしょう。吊るし切りはロープを使用して枝をおろすため、大掛かりな作業になるからです。また、松の木など観賞用の樹木は特殊な仕立て方になっているケースもあるため、業者に依頼したほうが美しい仕上がりになります。
剪定の費用相場は単価制か日当制

業者に剪定を依頼する場合、その費用は単価制か日当制かで異なります。単価制は、『木1本あたり○○円』と決められているため、1本だけ剪定してほしいなど数が少ない場合におすすめです。木の高さによっても費用は異なります。
一方で、日当制は職人1人につき『1日当たり○○円』となっています。剪定してほしい木の本数が多い場合は、単価制よりもお得になる場合があります。ただし、業者によって設定価格はまちまちなので、まずは見積りをとって比較するようにしましょう。
庭木の剪定業者をご紹介します
弊社では庭木や植木の剪定業者をご紹介しています。また、樹木だけでなく、草刈りやお花のお手入れなどお庭の総合的なメンテナンスができる業者もご紹介することが可能です。お問い合わせは無料となっていますので、弊社のフリーダイヤルまでお電話ください。メールでのご相談も大歓迎です。