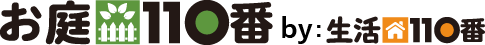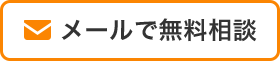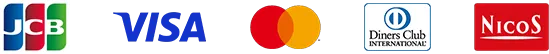金木犀(キンモクセイ)に限らず、剪定をおこなうことは見た目を綺麗にするだけでなく、樹木を元気に育てるための方法のひとつです。剪定をおこなうことは害虫の予防にも役立つなど、メリットがたくさんあります。
金木犀の花や香りをより楽しむためにも、剪定についての知識は必要不可欠です。正しい金木犀の剪定時期や方法についてご紹介しますので、金木犀がお庭にすでにある人や、これから植えようと検討している人は、ぜひ確認しましょう。
金木犀(キンモクセイ)の剪定時期は2月から3月
剪定をおこなう場合、樹木によってそれぞれ適した時期があります。金木犀の場合、剪定する時期を間違えてしまうと、花や香りを例年のように楽しめなくなってしまうおそれがあります。
香りや花を楽しむために、金木犀の剪定の方法や手入れの時期をきちんと把握しておきましょう。
金木犀の剪定時期は2月~3月と、11月も適しています
金木犀の剪定時期は、2月から3月が基本ですが、他にも11月にもおこなうことがあります。金木犀の花が咲くのは10月頃からです、花を楽しんだ後、11月頃に一度目の剪定をおこないましょう。花が咲く前に剪定をしてしまうと、花が咲くはずの蕾まで切り落としてしまいかねません。
2月から3月には、本格的に枝を剪定して樹形を整えるとよいでしょう。また、あまりにも葉っぱが密集していると、花の付き具合や香りに影響を及ぼします。適度に剪定をして、全体に日の光が当たるようにしましょう。
剪定という大切なお手入れで、金木犀がよく育つ!
金木犀の剪定は、樹木を均等に成長させるためには必要な作業です。剪定することで、害虫の予防にもつながります。
金木犀は特に成長の速度が早い樹木です。また、日陰でも育つことが可能な種類です。金木犀の剪定をせずに放置していると、あっという間に枝葉が伸びてしまいます。
枝葉が伸びることで、金木犀の周辺に植わっている植物の成長にえいきょうを及ぼしてしまうこともあります。金木犀よりも背の低い植物を近くに植えている場合は、その植物にもきちんと日が当たっているかを気にしてあげましょう。
金木犀を剪定してはいけない季節は?

金木犀の選定に適した時期をご紹介しましたが、反対に剪定をしてはいけない時期も存在します。剪定してはいけない時期に金木犀の剪定をおこなってしまうと、香りや花を十分に楽しむことができません。
金木犀の剪定をおこなう前に、きちんと把握をしておきましょう。
花芽をつける春~夏は、キンモクセイの剪定はNG
金木犀の蕾は、春から夏にかけて成長します。その時期に剪定してしまうと、枝だけでなく成長途中の花芽も切り落としてしまいます。そうするとせっかくの金木犀の花や香りを楽しめなくなってしまいます。
基本的に金木犀は剪定などの刈り込みに強い植物です。香りなど関係なくとにかく小さくしたいならば春から夏の剪定も構いません。ただ、急激に枝や葉を少なくしてしまうと、“枝枯れ”を引き起こしてしまうので気を付けましょう。
金木犀の花芽は、葉っぱの付け根にある
先ほどご紹介した金木犀の香りのもとになる花芽は、葉っぱの付け根にあります。花が咲いていない花芽の状態だと、じっくり見ないと発見できないでしょう。つまり、花芽の状態で迂闊に金木犀の剪定をおこなってしまうと、金木犀の花も切り落とすことになるのです。
金木犀をやむなく春から夏に剪定する場合は、葉っぱの付け根をよく観察して香りを楽しむために花芽が少ないものを選ぶとよいでしょう。
金木犀の剪定方法!
金木犀の剪定は、業者への依頼だけでなく、自分でおこなうことも可能です。金木犀は成長の早い樹木なので、毎年剪定するのが望ましいとされています。もし自分で金木犀の剪定をおこなえるようになれば、家計にも優しいですよね。
では、金木犀の剪定に必要なものや、具体的な剪定のやり方についてご紹介します。
剪定で必要なもの
金木犀の剪定には、以下のものを用意しましょう。
・軍手
金木犀の剪定に限らず、素手で樹木の剪定をするとケガをしてしまうおそれがあります。きちんと軍手を装着するようにしましょう。
・剪定ばさみ
金木犀の大体の形を揃えるときに使います。太い枝を切ることができる両手ばさみを選びましょう。
・植木ばさみ
細かい枝を切り落とすときに利用します。内側の込み入った枝を剪定する際にも使います
・脚立やはしご
手の届かない高さまで伸びた枝を切るときに使用します。脚立やはしごを利用する際は転倒などに十分注意するようにしましょう。
場合によっては脚立やはしご、剪定ばさみを用意する必要がないこともあります。自分が剪定する金木犀の大きさや、どの箇所を剪定するのかきちんと確認したうえで用意しましょう。
外側は年に1回、剪定しよう
金木犀は成長のスピードが速い植物です、きちんと日の当たる場所に植わっていれば、1年で約15cmも枝を伸ばします。植わっている場所にもよりますが、1年に1回剪定するのが理想と言われています。
金木犀の選定方法は大きく分けて2種類に分けることができ、それぞれ“外側剪定”と“内側剪定”と呼ばれています。
毎年の剪定が水腫押されている剪定は外側剪定です。金木犀の枝の長さを揃え、樹形を揃えます。金木犀は丸みを帯びた形が理想です。全体の長さを揃えたら、微調整をおこないましょう。
金木犀の剪定が初めての人や、あまり慣れていない人は内側剪定から始めましょう。なぜなら、金木犀は内側に不要な枝が集中しているからです。枝の向きが外側に向かっていない枝や、すでに枯れてしまっている枝を根元から切り落としましょう。
内側の枝を剪定することで、風通しがよくなり、日当たりがよくなるので、害虫の予防や成長の促進につながります。
内側は毎年やらなくてもOK
金木犀の内側剪定に関しては、毎年おこなう必要はありません。基本的に3から4年が目安です。あまり頻繁に剪定してしまうと、花の数が少なくなり、香りを楽しめなくなってしまいます。
金木犀剪定のコツは?花付きがよくなる手入れの仕方

金木犀の花がたくさん咲けば、その分香りを楽しむことができます。では、花をたくさん咲かせるためには金木犀の剪定をどのようにおこなえばよいのでしょうか。
不要な枝を見極めよう
金木犀の花が付いていない枝や、他の枝に付いた花の成長を妨げるような枝は切り落としましょう。剪定の時に切り落とすべき枝をいくつかご紹介します。
・懐(ふところ)枝
大きな枝ではなく、幹から直接生えている短い枝です。日があまり当たらないので、懐枝の成長はあまり期待ができません。放っておくと、空気がこもってしまい、害虫が住み着いてしまいます。
・逆さ枝
他の枝とは違い、幹に向かって伸びている枝です。この枝はそのまま成長すると、枝が絡まってしまい、外観が悪くだけでなく他の枝への日当たりにも影響を及ぼします。
・胴吹き枝
金木犀の幹から直接上に伸びている枝で、幹吹き枝とも呼ばれます。この枝を放置していると、金木犀全体、特に樹木の上部に栄養が行き渡りにくくなってしまいます。
金木犀の内側剪定をするときには、まずはこのような枝から切り落としましょう。
不要枝を払ってもまだ枝が多かったら、透かし剪定を!
先ほど紹介したような不要な枝を切り落としても、まだ枝の数が多いこともあります。その時は透かし剪定をしてみましょう。全体のバランスをみて風通しを良くするための剪定なので、初心者には少し難しいかもしれません。
どこを切ればいい?花が咲かない!そんな時は…
金木犀の剪定を自分でやることに不安がある人は、気軽に業者に依頼してみましょう。一度でも金木犀を剪定している現場を見学することで、自信や知識が身に付くでしょう。業者の人にコツなどを聞くことも可能です。
今まで自分で剪定をおこなっていて、花が咲かなくなった場合は、剪定に問題があるかもしれません。一度プロの目で見てもらい、適した剪定方法で剪定をしてもらいましょう。
まとめ
金木犀は病気などにも強く、育てやすい樹木のひとつです。そんな金木犀をより長く楽しむために、正しい剪定の方法や、時期などを把握しておくことはとても大切なことです。
金木犀の剪定は業者に依頼をしなくても自らおこなうことが可能です。興味がある人は一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか?