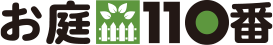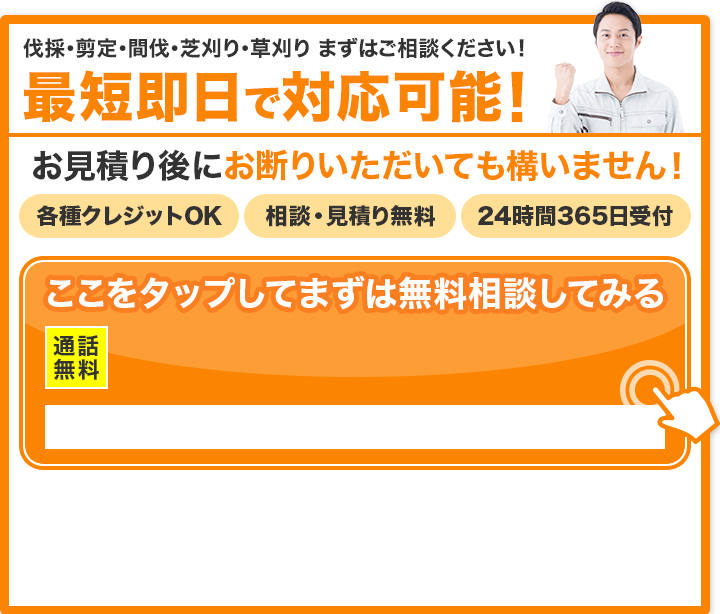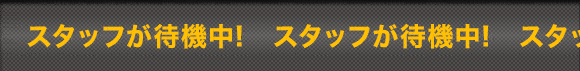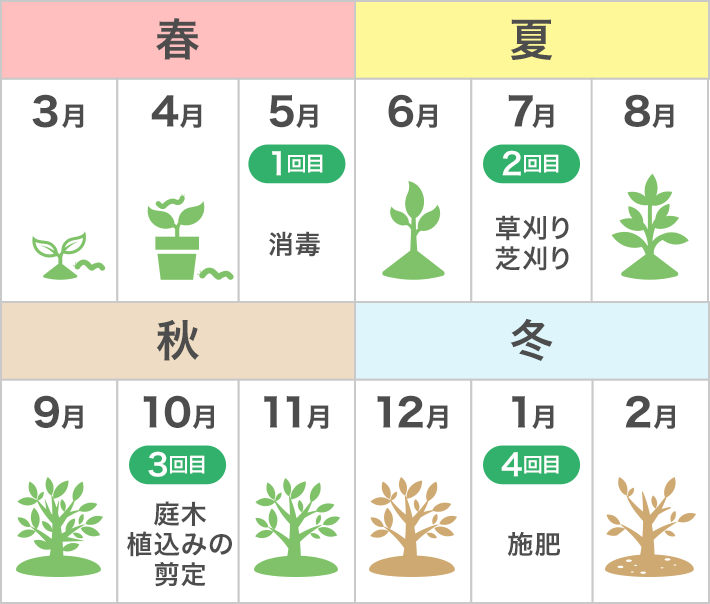最新情報・レポート
目次 杉伐採の時期や方法って…?安全に作業するための3つのポイント 杉の伐採後には何をすべき?必要な処理をまとめます 杉を伐採すれば花粉症から解放される?!なぜ伐採は進まないのか 杉は日本の至るところ育っている樹木です。時間をかけて大きく育つ杉は、50年以上たつと20メートルを超える巨木に成長します。そんな巨木は、60年ほど成長したあとは木材にするために、そして...
八朔は1~4年目と5年目以降で剪定方法が異なります。八朔は1~4年目は苗木から成木になる生長段階で、5年目以降に成木へと生長します。時期ごとに生長具合が異なるので、それぞれの時期に適した剪定をおこなう必要があるのです。 このコラムでは、八朔の剪定時期や方法についてご紹介しています。そのほか、八朔の上手な栽培方法や八朔を使ったおすすめのメニューについてもご紹介しているので、試してみてはいか...
庭木などを剪定する際、剪定シートを敷いておくと切った枝葉の後処理が楽になります。剪定シートを敷くことにより、切り取った枝葉が地面に散らばらないからです。 また、ほうきで掃いても小石や土が混ざってこないので、枝葉のみをゴミ袋に入れて処分することができます。このコラムでは、剪定シートの種類や選び方をご紹介しています。購入するときに、どれを選べばいいかを知るための参考にしていただけると幸いです...
銀杏を剪定でスッキリとしたきれいな樹形にしたいなら、「武者立ち」という仕立て方がおすすめです。武者立ちは主幹を途中で切って脇枝を上に伸ばさせる形の仕立て方です。この形にすることで銀杏が上に大きく伸びすぎるのを抑え、枝の量を適度に減らしてバランスのよい形に整えることができるのです。 当記事では銀杏の剪定方法や剪定時期を解説しています。また、業者に剪定を依頼した場合の費用相場も解説しているの...
ローズマリーは観葉植物としてはもちろんのこと、ハーブとしても活用されている植物です。手軽に育てられるイメージをもたれるかもしれませんが、ローズマリーを剪定するには時期に気をつける必要があります。 適切な時期以外に剪定をおこなうと、枯れてしまうおそれがあるからです。そこで今回は、ローズマリーの剪定時期や方法についてご紹介していきます。より多く収穫するために、挿し木の手順についてもお伝えして...
つるバラのアンジェラの剪定は、誘引する前におこなっておきましょう。なぜなら、剪定をおこなわないと枝先が細くなり出てくる芽が小さくなってしまうからです。そして枝が混み合うと、花の数が少なくなってしまいます。 当記事では、つるバラアンジェラの剪定方法や誘引について解説していきますのでぜひ参考にしてください。 剪定や誘引をおこない、毎年きれいな花が咲くようにしていきましょう。 目次 ...
エニシダの剪定は、花が終わってすぐの6月~7月上旬の時期におこないましょう。花が終わって日数がたった後に剪定をすると、翌年の花数が減ってしまうかもしれないためです。 今回はエニシダの剪定方法などをくわしく解説します。エニシダは正しい方法で大切に育てれば10年は楽しめる植物です。本記事を参考いただいて、できるだけ長くエニシダを観賞しましょう。 また、エニシダの花が減る心配がないよう対策し...
基本的に、カツラの定期的な剪定は必要ありません。しかし、枝や幹が伸びすぎている場合は、形を整えるために剪定をおこなったほうがよいでしょう。 なぜなら、カツラは樹高10メートル以上に生長することもある高木であるため、放置しているとどんどんと枝や幹が伸びていってしまうからです。そうなると、手入れをおこなうのもひと苦労になります。 ここでは、カツラを剪定する時期や方法について解説。さらに...
ボケの木の剪定は年2回、花が咲いたあとと秋ごろにおこないます。咲いた花をそのままにしておくと実がなり栄養分を余分にとられてしまうため、摘み取る必要があるからです。また、秋ごろの剪定は樹形を整えて健康的に育てるためにも大切です。 ボケの木の剪定を適切な時期におこなって、毎年花を楽しめるようにしましょう。今回の記事では、ボケの木の剪定方法や挿し木のやり方や育て方のコツについてもお伝えしていき...
コナラを庭木として育てるのであれば、風通しをよくするための「剪定」をおこなうようにしましょう。なぜなら、コナラはやや乾燥ぎみの環境を好むため、剪定により健康的に栽培することができるからです。さらに、剪定は病気・病害虫対策にもなります。 この記事では、コナラの剪定時期や方法について解説。また、健康的に育てるために大切な普段のお手入れ方法や病害虫対策もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださ...
桜の伐採は、落葉後の11月下旬~3月下旬頃におこないましょう。 落葉後は木が休眠状態になり、内部の水分が少なくなるからです。 焼いて処分をする場合は、水分が少ないほうが作業しやすくなります。 今回は桜の伐採時期・方法をわかりやすく解説します。 伐採前のお祓いについても触れているので、気になる方はあわせて読んでみてください。 大きな桜の木の伐採や処分でお困りの際は、お庭...
「自力で椿の剪定を最後までやってみたい」 「椿の花付きを良くしたい」 このように、椿の剪定にお悩みではありませんか? 椿の剪定期間は短いため、タイミングを逃して花芽を切ってしまわないように気を付けましょう。 花芽を切ると花の数が減ってしまい、美しい椿の花が少なくて寂しくなってしまいます。。 このコラムでは以下の内容を解説していきます。 椿の剪定方法 椿の剪定時...
「邪魔な竹を処分したい」 「竹林の竹をまとめて伐採したい」 このように、竹の伐採にお悩みではありませんか? 竹は一般的な樹木と比べると伐採しやすいです。 樹木の伐採はのこぎりで幹の両側から切り口を入れるなど手間がかかりますが、細い竹は鎌や鉈で切り倒すことも不可能ではありません。 このコラムでは以下の内容を解説していきます。 竹の伐採方法 竹の伐採時期 伐採し...
お手入れが行き届かなかったり枯れてしまったりして、松の木の伐採をお考えの方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、松の木を切るときに気になる縁起や、伐採の手順を解説します。 松の伐採を安全におこないたい方は、お庭110番にご相談ください。 お祓いから木の処分まで、すべて任せられる業者をご紹介いたします。 目次 松の伐採前に確認したいこと! 「お祓い」と「伐...
みずみずしい実をつけるブドウの木は、日本全国で育てることができ、観賞用にも食用にも適した果樹です。 せっかく庭で育てるなら、家でブドウ狩りができるくらい上手に育てましょう。 樹形のいいブドウを育てて実を楽しむためには、適切なお手入れが必要です。 生長具合に合わせたお手入れができれば、ただブドウの実が付くだけでなく、栄養のつまったおいしい実をつくることができます。 本記事で基本の...
ヤシ科に属するシュロ(棕櫚)は、南国にあるようなイメージがありますが、ヤシの種類の中でも寒さに強いため、日本でも広い地域でお家の庭木として愛されています。 しかし、こまめなお手入れをせず放っておくと、樹高が高くなり自分で管理できなくなる場合があります。 大きく生長したシュロの木は邪魔になっても簡単には撤去できません。2通りの伐採方法を確認して、ご自宅の状態に合う方法で撤去しましょう。 な...
杉の伐採費用は、工事費、人件費、重機の使用費の3つの合計で決まります。 それぞれの相場を知っておくと、業者から見積りをとったときに、価格が適正かどうか判断しやすくなりますよ。 今回は杉の伐採費用の内訳を詳しくご紹介します。 業者への依頼を考えている方は、依頼前にぜひ読んでみてください。 お庭110番では、杉の剪定に関するご相談や、お見積りなどのご依頼を承っております。 ま...
金のなる木が思った以上に大きくなってきたら、お好みの位置で剪定してしまっても問題ありません。どこから剪定しても、切ったところからまた新しい枝が生えてくるからです。ただし、いきなり半分以下に小さくしてしまうと枯れることがあるので、切る量には注意が必要です。 このコラムでは、金のなる木の剪定方法についてご紹介しています。また、葉がポロポロ落ちるなどのトラブルがある場合の正しいお手入れ方法や、...
庭木としてケヤキを育てる場合、若木のうちに大きくならないよう定期的に剪定をおこなう必要があります。ケヤキは生長すると高さ30mほどにもなる木です。広い公園などであればとくに問題はありませんが、自宅の庭では広さが限られているため、大きく育てることが難しいからです。 また樹高が高すぎると、混み合った枝葉などを剪定することが困難になってしまいます。そうなってしまう前に、当記事でお教えするケヤキ...
コノテガシワを刈り込むなど、強めの剪定をする場合は3月におこないましょう。3月以外の時期に強い剪定をするとダメージに耐えられず、枯れる原因となってしまうからです。 ただし、軽めの剪定なら時期を問わずいつでもおこなうことができるため、枝が数本飛び出るなど気になるところがあれば、その都度切り落としても構いません。 このコラムでは、コノテガシワの剪定についてわかりやすく解説しています。ま...