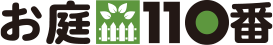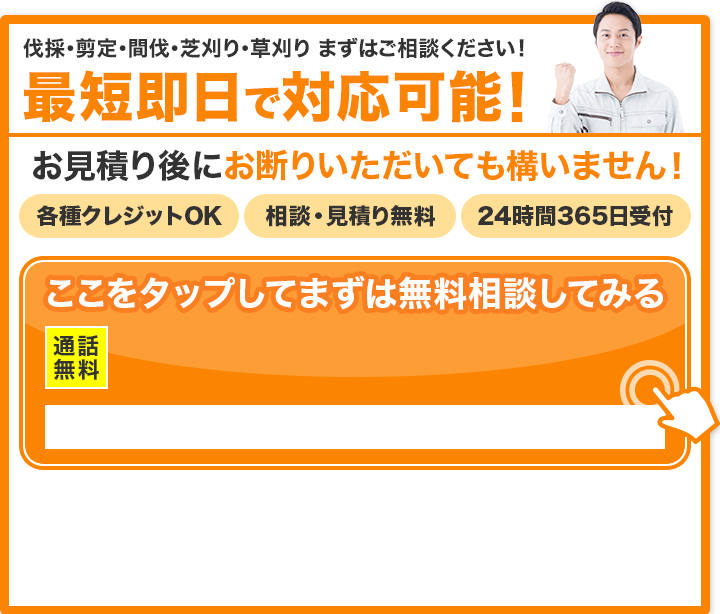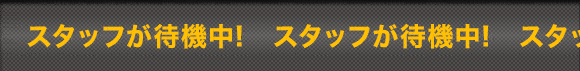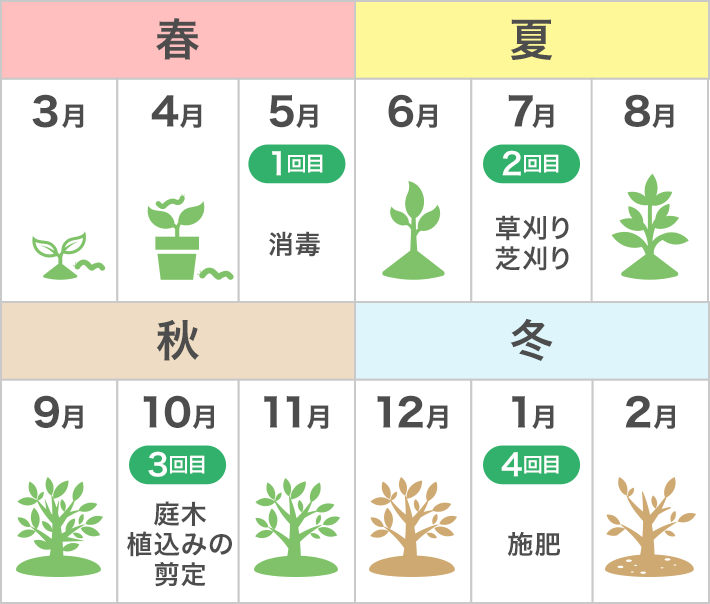最新情報・レポート
夏みかんを剪定するときは、新芽が出る前の2月~3月ごろにおこないましょう。新芽が出る前の時期は、枝が伸びる方向を見極めやすく、生長したときの樹形を整えやすくすることができます。 また、新芽が出始める4月以降に剪定をおこなうと、夏みかんに大きなダメージを与えてしまうおそれがあるためです。そのため、夏みかんの剪定は遅くても3月までに終わらせるようにしましょう。 この記事では、夏みかんの...
夾竹桃はすべての部分に非常に強力な毒をもっています。 毒の強さは、葉や枝に肌が少し触れただけでも炎症を起こしてしまうほどです。 だからこそ夾竹桃の剪定を検討している方は、当記事で毒の危険性や正しい剪定方法をしっかりと理解しておきましょう。 正しい知識を身に着けていれば自分の身を守ることができますし、作業中の迷いや不安が減って作業がスムーズに進みますよ。 それでもやはり「毒が...
切り戻し剪定は、おも木の高さを抑えて樹形を整える目的でおこなう剪定です。また、木の成長を促進させるためにも必要な作業なのです。 枝の途中で切り詰めると、そこから新たな枝が伸びて若返らせることができます。花木の場合は切り戻し剪定をおこなうことで、より大きくたくさんの花を咲かせることにつながります。 切り戻し剪定は、どういった枝を切っていけばよいか知ったうえでおこなっていきましょう...
西洋ニンジンボクを剪定する場合は、枯れたり病気になったりしている枝を取り除き、適度な大きさを保つ程度にしておきましょう。なぜなら西洋ニンジンボクの枝は少なく、樹形が乱れるということはそれほどないからです。 このコラムでご紹介する剪定方法を参考にしていただき、西洋ニンジンボクを育ててみてください。また西洋ニンジンボクをうまく栽培するコツなども解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。健...
しだれ桃を剪定するときは、生長期や開花期を避けて、休眠期におこなうことが大切です。生長期や開花期にしだれ梅の剪定をおこなうと、樹勢を落としたり花芽を切り落としたりしてしまうおそれがあります。 しかし、休眠期の剪定であれば、剪定のダメージを少なくすることができるのです。そのため、しだれ桃を剪定するのであれば、休眠期である11月以降におこなうようにしましょう。 この記事では、しだれ桃の...
プルーンの木の剪定は夏と冬の2回おこないますが、それぞれ剪定方法が異なります。 夏は風通しをよくして病害虫を予防することがおもな目的になるので、枝葉を間引く間引き剪定が中心です。一方冬は収穫に向けて実つきをよくすることがおもな目的になるので、枝を短く切りそろえて実がつきやすいようにします。 当記事を参考に、プルーンの木の剪定にチャレンジしてみましょう。また、日常のお手入れや実の受粉...
柿を育てていると、徒長枝という上へと伸びる長い枝がいくつも生えてくることがあります。柿の剪定はこの徒長枝をばっさりと切り落としてしまうことがポイントです。 徒長枝は伸びる力が強く、たくさんの栄養を使ってしまいます。そうするとせっかくの実に栄養が行き渡らず、味や大きさに影響を与えてしまうのです。 この記事では、柿の剪定方法とあわせて、おいしい実を収穫するコツについてもご紹介していきま...
レンギョウの剪定は年に2回、正しい時期におこなうことが大切です。なぜなら、間違った時期に剪定してしまうと翌年の花が咲かなくなってしまうこともあるからです。当記事ではレンギョウの剪定時期や剪定方法について解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。 目次 レンギョウの剪定時期と剪定方法について 剪定時期は年に2回ある! 剪定方法 レンギョウを育てる環境について 日当たり...
「イチイの木が大きくなりすぎてしまって手に負えない」 「イチイの木の枝葉が伸び放題で見栄えが悪い」 こんなお悩みを抱えていませんか。 せっかく植えたイチイの木、きれいに整えるのはもちろん健康的に育てたいですよね。 そこで今回はイチイの木の剪定方法や成功のコツ、基本のお手入れ方法をまとめました! 初めての方にもわかりやすく解説するのでぜひ最後までご覧ください。 お庭110番で...
クレマチスは手入れの仕方を間違えると、花が全然咲かなくなってしまうほど扱いが難しい植物です。もし花が咲かなくて困っているのであれば、まずはクレマチスの剪定方法を見直してみましょう。 なぜなら、クレマチスの剪定はタイプによって方法が違ってくるからです。この記事では、タイプ別で異なるクレマチスの剪定方法について詳しく解説します。ほかにも、花を咲かせるために気をつけたい栽培方法のポイントなども...
ウバメガシの剪定は、「透かし剪定」で生長の妨げになる枝葉を取り除き、「刈り込み剪定」で樹形を整えましょう。ウバメガシを剪定せず放っておくと、枝葉が多くなり日当たりや風の通りが悪くなるため、ウバメガシが枯れてしまうおそれがあるからです。 また病害虫も発生しやすくなるので、剪定して未然に防ぐことが大切なのです。当コラムでご紹介するウバメガシの剪定方法を参考にしていただき、見栄えがよく丈夫に育...
「イトヒバがぼさぼさで見栄えが悪い……」 「イトヒバを剪定したいけどどうやればいいの?」 当記事をご覧の方はこのようなお悩みを抱えている方が多いと思います。 そこで今回は、イトヒバの剪定時期と方法、きれいな樹形を作るコツをまとめました! 初めての方でも安心して作業できるように、できるだけ詳しくわかりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。 その他、イトヒバの状態ごとに適...
ユッカの剪定は5~6月の暖かくなり始めた時期におこないましょう。暖かい時期はユッカの成長力が強い時期でもあるので、枝や幹をばっさりと剪定してしまっても、ダメージを回復することができます。 この記事では詳しい剪定方法や、育て方についてもご紹介していきます。ユッカを育てている方や、これから育てようと思っている方は、育て方をひとつひとつ確認してみてください。 目次 ユッカの剪定...
しだれもみじの剪定時期でベストなのは冬!とくに落葉直後がおすすめです。 この時期なら作業負担が少なく、しだれもみじのダメージを抑えつつスッキリ剪定できます。 とはいえ、どうしても春夏や秋にしだれもみじを剪定したい場合もあるでしょう。 冬以外の剪定は二度手間や紅葉への悪影響といったリスクが多いため、本記事でしっかり対策をチェックしてから着手してくださいね。 剪定でしだれもみじ...
もみの木の剪定では、基本的な枝葉の剪定に加えて、高さを抑えるための「芯止め」もおこないましょう。 もみの木は生長が早いため、放置しているとどんどん大きくなり、手入れが難しくなってしまいます。さらに手入れできない状態が長く続くと、病害虫が発生し枯れてしまうおそれもあるので、適度な大きさに調節しておくことが大切なのです。 しかし芯止めは高所での作業になるので、できれば業者に依頼するのが...
銀木犀を剪定するときは、剪定時期に注意することが大切です。銀木犀の剪定時期は、11月ごろとなっているので、この時期に剪定をおこなうようにしましょう。 銀木犀は4月ごろから開花の準備を始め、9月~10月ごろが開花時期となっています。そして、花が咲き終わる時期が11月ごろとなっており、この時期は剪定をしても翌年に悪影響を及ぼさないのです。 そのため、銀木製を剪定するときは遅くても12月...
ラカンマキの剪定方法は、生け垣にしたいか庭木にして育てたいかによって異なります。なぜならどんな形に仕立てたいのかによって、切る枝も方法も違ってくるからです。 当記事では、そんなラカンマキの剪定方法や剪定する時期について解説していきます。 自分で剪定する際の注意点などもご紹介しますが、剪定作業だけでなく仕立て方からプロに相談したい場合はお庭110番にお電話ください。お庭全体のバランスなど...
観葉植物として人気のドラセナ。 室内で育てている方のなかには「大きくなりすぎて天井に届きそう!」とお困りの方も多いのではないでしょうか。 ドラセナは切り戻し剪定をおこなって高さや枝ぶりを管理する必要があります。 ドラセナは生育旺盛で上へ上へとグングン伸びていくため、適度な高さに保つには剪定が欠かせないのです。 剪定をしないで放っておくと、葉が密集して風通しが悪くなり、害虫も発生...
ウツギの剪定は、花が咲いたあとにおこないましょう。剪定に適した時期は、花後と落葉期です。ウツギは花芽が付く時期に剪定すると翌年咲く花が減ってしまいます。そのため、正しい剪定時期でおこなうことが大切なのです。 毎年ウツギのかわいらしい花が咲かせられるように、正しい剪定時期を知っておきましょう。そこでこの記事では、ウツギの剪定時期や方法についてご紹介します。また、剪定した枝を使った挿し木の方...
ユスラウメの木の剪定は混み合った枝や葉などを間引く間引き剪定や、古い枝や細い枝を切り落として樹形を整える剪定をおこないましょう。 枝を切りすぎてしまうと木が弱ってしまい、実のつきが悪くなることがあるからです。 当記事を参考に正しい剪定をおこないユスラウメの木を健康的に育てましょう。また、美味しい実をならせるための育て方のコツや、実の収穫時期、活用方法についても解説しますので、合わせ...